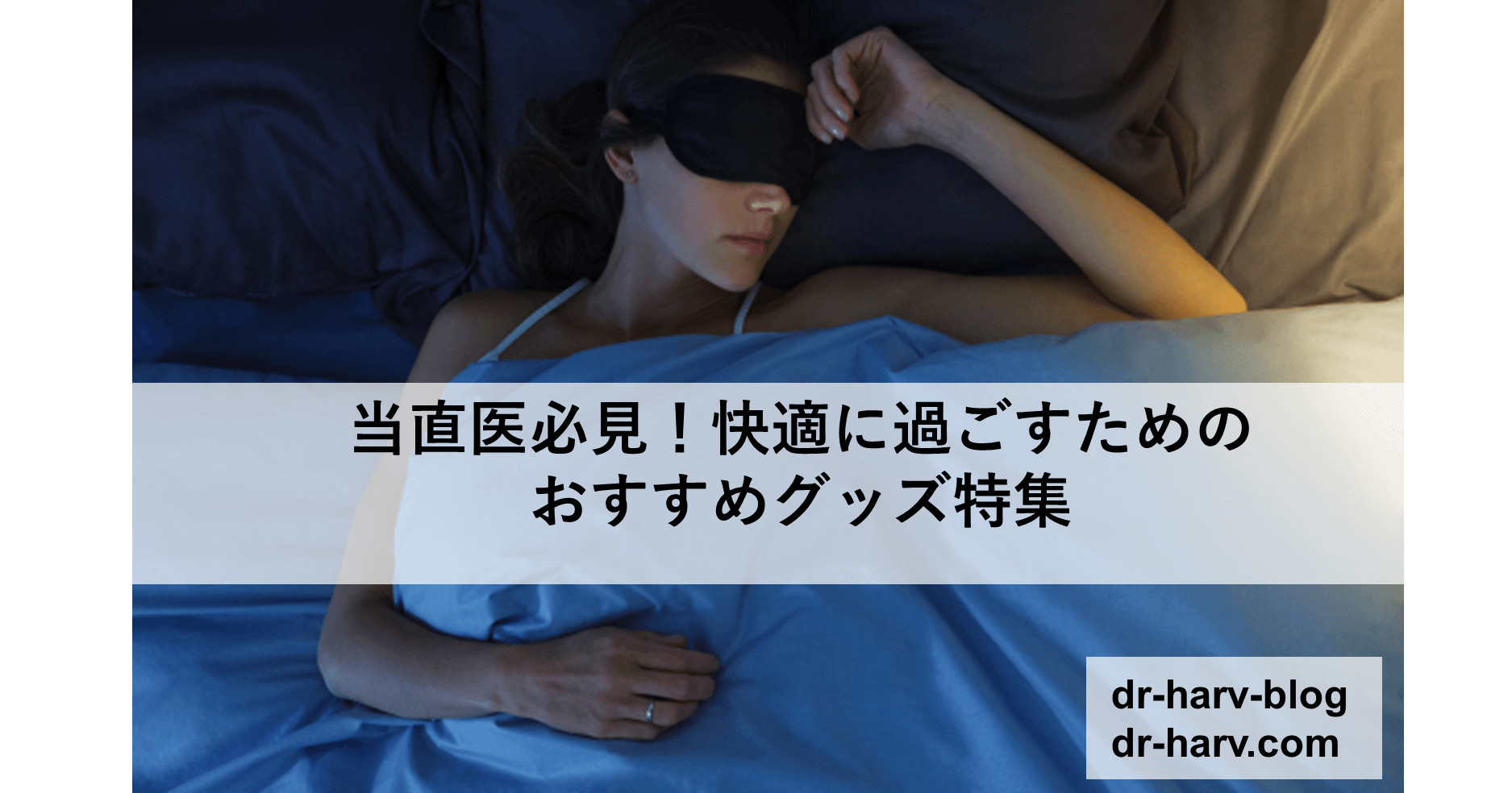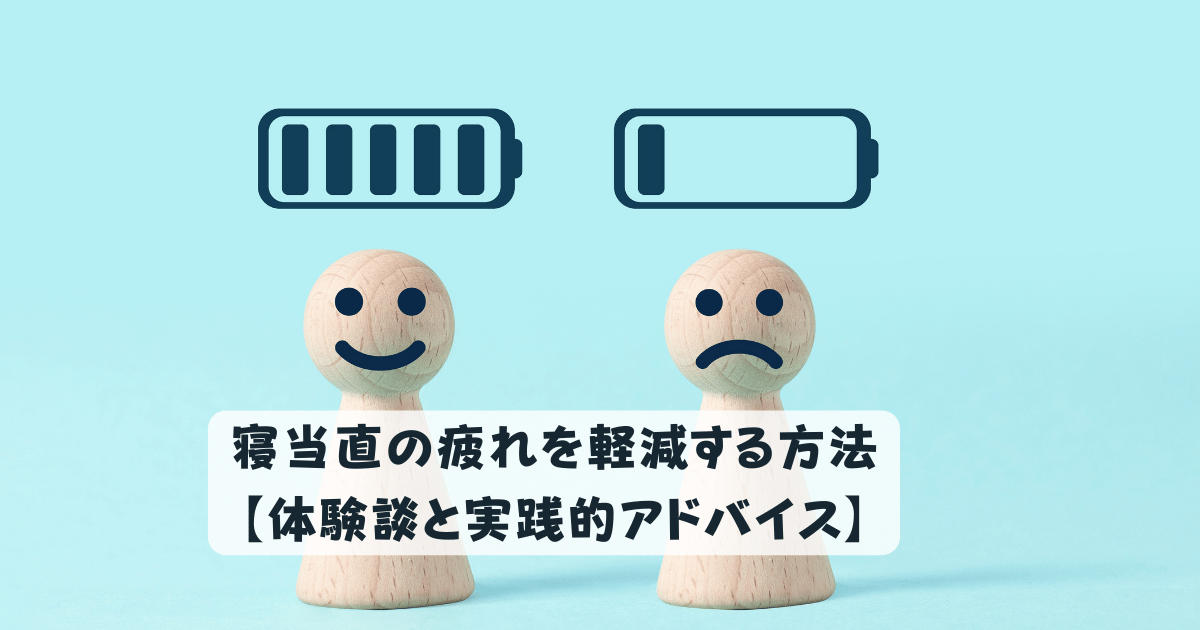「寝当直だから休めるはずなのに、なぜか疲れが残る…」
そんな悩みを抱える医師の方へ。この記事では、実際に寝当直を経験した医師の視点から、“見落とされがちな疲労の原因”と“具体的な軽減・回復法”を紹介します。
寝当直後疲労の3大原因
疲労の背景は主に3つです
睡眠の「量」ではなく「質」の低下(睡眠断片化)
これが最も一般的な原因です。たとえ合計で7時間眠れても、1〜2時間ごとにPHSのコールや物音で意識が浮上すれば、脳が真に休息できる深いノンレム睡眠のステージに到達できません。睡眠が細かく分断されることで、脳は休息をとれないまま、時間だけが過ぎていくのです。
環境要因による、無意識のストレス(覚醒レベルの維持)
当直室のベッドが合わない、空調が効きすぎている、廊下の音がうるさい…。こうした不快な環境は、我々が意識していなくても、自律神経系に影響を与え、交感神経を優位にさせます。身体は常に「いつでも起きられる」という低いレベルの緊張状態を強いられ、完全にリラックスすることができません。
精神的負荷(オンコール・マインド)
たとえPHSが一度も鳴らなくても、「いつ鳴るか分からない」という精神的な待機状態、いわゆる「オンコール・マインド」は、それ自体が認知的なリソースを静かに消耗させます。完全にスイッチをオフにできないこの状態が、見えない疲労として蓄積していくのです。
【治療プロトコル】原因別・戦略的な回復術
これらの原因に対し、具体的な「処方箋」を提示します。
処方箋①:睡眠の質を最大化する「環境構築術」
睡眠の断片化と環境ストレスという病態に対し、最も有効な治療は、劣悪な当直室を、自らの手で
「最高の睡眠環境」へと変えることです。
- 枕・アイマスク・耳栓: 睡眠の質を左右する「三種の神器」です。光と音を完全に遮断し、自分に合った枕で身体的ストレスを軽減します。
- シャワー: 短時間でもシャワーを浴びることは、血行を促進し、気分をリセットする強力な治療法です。
▶【関連記事】当直中のシャワー、最適なタイミングとリスク管理術
処方箋②:精神的負荷を軽減する「自己マネジメント術」
「いつ呼ばれるかわからない」という不安は、事前の準備とスケジューリングである程度コントロールできます。
- 1週間のリズムを設計する: 当直の日を基準に、その前日や翌日の業務量を調整する。重要な手術やタスクの前後に当直を入れない、といった計画的なスケジュール管理が有効です。
- 情報収集とシミュレーション: 当直開始時に、入院患者の状態や、コールがありそうな患者の情報を重点的に把握しておくことで、「不意打ち」のコールを減らし、精神的な準備ができます。
処方箋③:当直明けの「ゴールデンタイム」を制する回復戦略
当直で受けたダメージを、いかに速やかに回復させるか。当直明けの数時間の過ごし方が、その後の1週間のパフォーマンスを左右します。
- 帰宅後の仮眠: 長時間寝るのではなく、1〜2時間の質の高い仮眠で、体内時計のズレを最小限に留めます。
- 栄養補給: 疲労回復を助けるビタミンB群や、良質なタンパク質を含む食事を意識して摂取します。
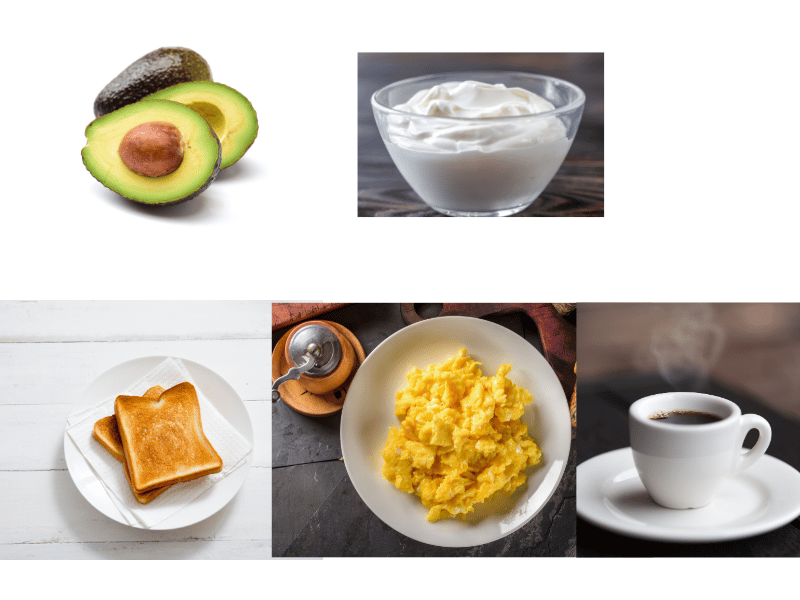
【私の症例】私が「当直明け外来」をやめた理由
私自身の話をすると、当直明けの日は、どうしても頭がボーッとして、思考のキレが鈍ります。そして何より、ストレス耐性が著しく低下し、普段なら何でもないことでイライラしやすくなることを自覚していました。
予約外の患者さんや、難しい要求をする方に対して、冷静な対応ができない。その一瞬の感情の乱れが、患者さんとの信頼関係を損ない、ひいては医療ミスに繋がらないとも限らない。
そのリスクを考慮した結果、私は、自分のパフォーマンスが100%ではない当直明けの外来業務は、担当しない、という判断をしました。これもまた、医療安全のための、私なりのリスクマネジメントです。
まとめ:自らの不調を、論理的にマネジメントする
「寝当直なのに疲れる」という感覚は、決して気のせいではありません。それは、睡眠の質の低下、環境ストレス、精神的負荷が絡み合った、明確な原因のある「症候群」です。
その原因を、我々が得意とする「鑑別診断」の思考法で一つひとつ特定し、適切な「治療(対策)」を施していく。自らのコンディションを論理的にマネジメントすることこそ、長く医師として走り続けるための、最も重要なスキルなのかもしれません。
あわせて読みたい:当直を乗り切るための総合戦略
効果的な休憩方法:
- 短時間でも深く眠るために、耳栓やアイマスクを利用して安眠環境を整えることが重要です。
ストレッチや軽い運動:
- 体をリフレッシュさせるために、軽いストレッチや運動を行うことで、血行を促進し、疲労を軽減します。
- シャワーも重要ですよね
栄養補給と水分摂取の重要性:
- 栄養バランスの取れた食事と十分な水分補給を心がけることで、体力を維持します。
耳栓、アイマスクなどの安眠グッズの利用:
- これらのグッズを利用することで、周囲の音や光を遮断し、質の高い睡眠を取ることができます。