「医学書は、通読するものではなく、辞書のように、引くものだ」
この、あまりにも、もっともらしい、合理主義的な、言説が、現代の、医学教育の、主流となっています。
しかし、本当に、そうでしょうか。
この記事では、この「通読=時間の無駄」という、風潮にあえて異を唱え、一冊の偉大な成書を最初から最後まで、読み通すという一見非効率な行為の中に、隠された計り知れない価値について、僕自身の経験を基に語ります。
「拾い読み」と「通読」、その、目的の、違い
まず、2つの、読書スタイルを、我々、医師の、業務に、例えて、その、本質的な、違いを、定義します。
通読(成書の、読破)これは、いわば「病理診断」や、「基礎研究」に近い、行為です。疾患群、全体の体系的な知識を深く理解するための、知的探求。直接的な、リターンは、すぐには、得られないかもしれません。
拾い読み(UpToDateや、ガイドラインの、参照)これは、いわば「救急外来」での、医療です。目の前の、特定の、患者(臨床疑問)に対し、最も、早く、的確な、答え(治療法)を、見つけ出すための、極めて、効率的な、情報検索。日々の、臨床業務に、不可欠な、スキルです。
なぜ、我々は、それでも、成書を、読むべきなのか?
この、一見、非効率な、行為が、もたらす、3つの計り知れないリターン。
① 知識の「地図」を、手に入れる
日々の「拾い読み」で、得られる、知識は、いわば、点です。通読は、それらの、無数の、知識の「点」を、結びつけ、分野全体の、鳥瞰図、すなわち、壮大な「地図」を、我々の、頭の中に、描き出してくれます。この、地図が、あるからこそ、我々は、未知の、症例に、遭遇した時にも、道に、迷わなくなるのです。
② 巨人の、肩の上に、立つ
ハリソンのような、偉大な、成書は、何世代にもわたる、先人たちの、知の、結晶です。その、目次や、構成、そして、文章の、一つひとつに、彼らが、どのような、思考の、変遷を経て、現在の、標準治療を、築き上げてきたのか、その、歴史的な、文脈が、刻まれています。通読とは、その「巨人の、肩の上に、立つ」ための、最も、誠実な、方法です。
③ 未知との、遭遇(セレンディピティ)
「拾い読み」では、我々は、自分の、探している、情報にしか、出会えません。しかし、「通読」の、旅の、途中では、自分が、探しても、いなかった、全く、新しい、知識や、研究の、アイデアと、偶然、出会うことができます。この、セレンディピティこそが、我々の、知的、好奇心を、刺激し、新しい、扉を、開いてくれるのです。
では、いつ、どう、読むか?
もちろん、多忙な、研修医時代に、ハリソンを、通読するのは、現実的では、ありません。 これは、キャリアの、節目、節目で、まとまった、時間を、確保し、挑むべき、知的な「巡礼」です。
- 専門医試験を、終えた、直後
- 新しい、サブスペシャリティの、分野に、足を踏み入れる、その、最初の、タイミング
- 大学院での、研究が、始まる、その、導入期
などが、最適な、タイミングと、言えるでしょう。
医学書をおトクに買うには?
医学書は正直高いです。高いですが、仕事で使う道具です。プロは道具にこだわるもの。
医者の経験、専門性によって必要とする書籍や媒体は変わってくることでしょう。少しでも医学書をおトクに購入するための情報をまとめているので、こちらの記事も参考いただければ幸いです。
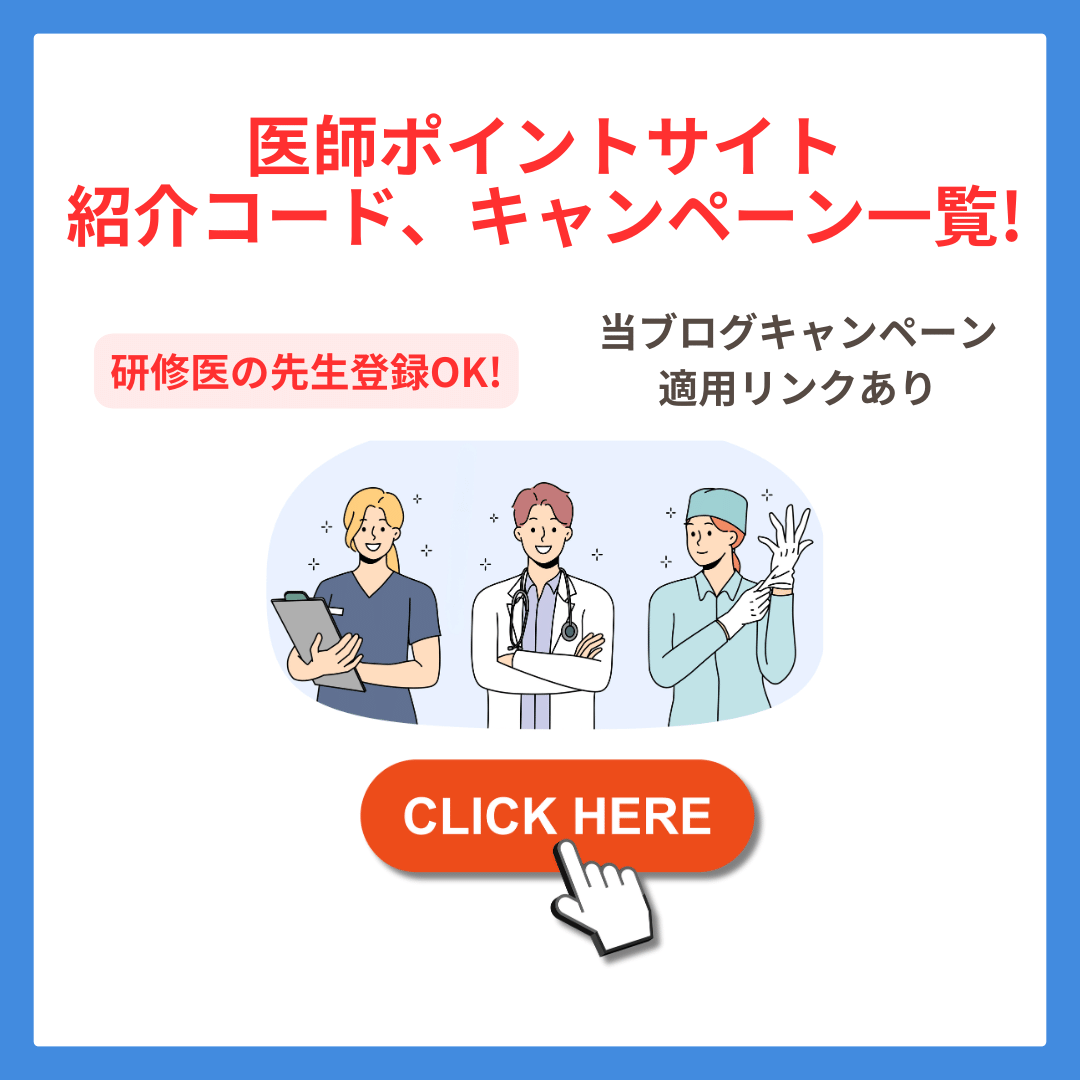
まとめ:非効率の、中にこそ、本質的な、学びが、ある
日々の、臨床で、求められるのは、「拾い読み」の、スピードと、効率性です。 しかし、時として、立ち止まり、一冊の、成書と、深く、向き合う、という、一見、非効率な、時間。こういったものも趣があるものです。
